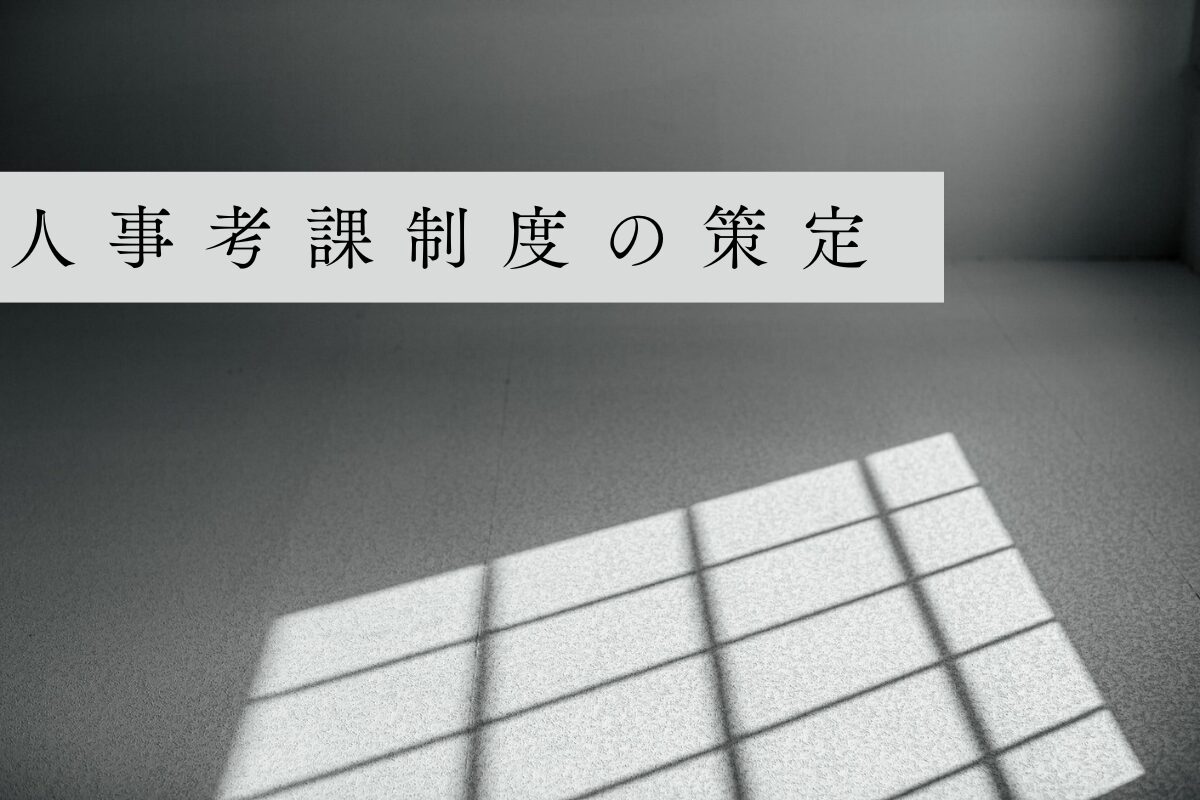ブログ
体現する気のない理念ほど無駄なものはない
コーポレートリブランディング
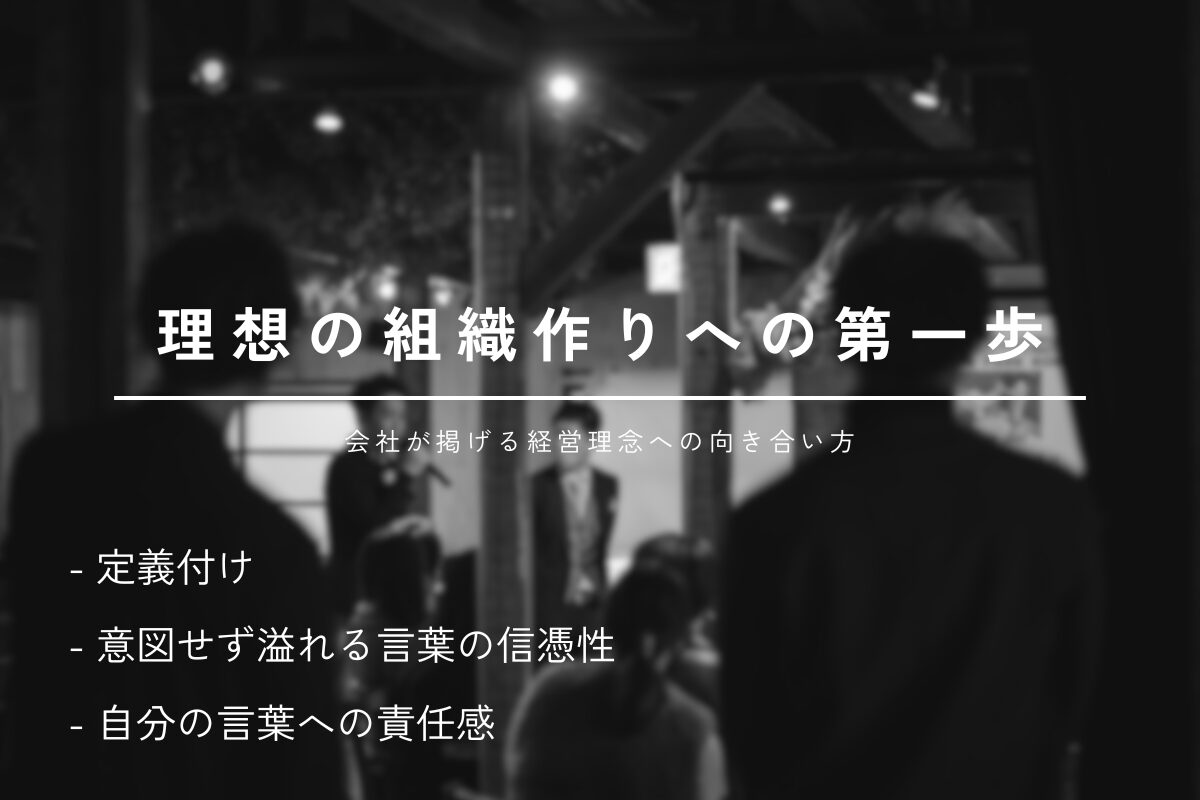
これはぼくが様々な会社を見てきた中で、何度も何度も思ってきたことでもあります。
なので今日のテーマは【経営理念】
Mad.の親会社であるnano human promotionの理念を掘り下げてみたいと思います。
定義しなければ始まらない
「人にきっかけを創る会社」
これは、nanoの経営理念の中の“コンセプト”にあたります。
「nanoは人の会社である」
これはぼくがnanoへ入社した当時から変わらずにある根底の想いではありますが、
ある日のある質問が会社に大きな変化をもたらすことになります。
「nanoが人の会社なことはわかったけど、nanoは人をどうしたいの?」
ぼくはこの質問を弊社創業者(現 会長)が投げかけられた場に同席しており、
いつも通りかっこよく答えることをイメージしておりました。
が、
「人を、、、。」と、今まで言葉に詰まるシーンなんて想像もできなかった会長が、
すぐには答えることができませんでした。
ぼくはあまりのショックに、その後のことはあまり覚えていません。
今思えば「自分たちは人の会社です!」と伝える会社の抽象度を目の前にすると、
何個でも質問は浮かんできますし、その時に突っ込まれることは当たり前だったと改めて思います。
ただ、その時のぼくは人を大切にするnanoのスタンスを愛していたがあまり、
思わず会長に「何も考えていないんですか?」と投げつけたことだけは覚えています。
ただ冷静に考えると、会長が何も考えていない訳がありません。
その時のぼくの思考も、生意気ではありますが間違っていたとは思えません。
では何が問題だったのか?
答えは
「いくらでも語れるほど会長の想いはあるけれど、それを定義できていなかった」
ここです。
あくまで「言語化」ではなく「定義」できていなかったことが原因なのです。
「人の会社」
→「人が好きな会社」
→「仲間を大切にする会社」
→「お客様第一な会社」
方向性は似た雰囲気ではありますが、全く捉え方や行動が変わってくることは明らかです。
これでは会社としてメンバーが同じ方向へ歩いていける訳がないのです。
こんなコンセプトに意味はないですよね?
意図せず溢れる言葉の信憑性
まずおこなったことは「ストーリーの言語化」です。
会長と社長に対してしつこいほどにヒアリングをし、
nanoに関わる細かいスタンスや思考、どのように感じながら働いてきたのか、逃げ出したかったエピソード、
苦しかった日々などを思い出していただきながら、ブワッとひたすら文字に起こしていきました。
そうすることでぼんやりと見えてきた「何か。」
この「何か」を言語化していきながら、明確にすることが「定義付ける」ということです。
大枠の言葉が見えてきたあとは、言葉を「削る」作業です。
必要のない言葉を削り、必要のない思考を削る。
追加することなく、引いていくことで、ぼんやりの正体が見えてきます。
こうして生まれて1つの言葉が「きっかけ」と言うワード。
会長も社長も共通していたことは「すべての人に向き合う」というスタンスです。
相手がどのような人間であれ、どんな過去があったとしても、否定せずに話を聞き、必ずその人が喜ぶ付加価値を提供する。
言葉にすることが苦手な2人だったはずなのに、自然と溢れ出るものがありました。
自身の言葉に責任を持つ
この言葉が生まれたことで、nanoとしてより具体的に動くことができ、
より実感的にビジョンに向けて走り出すことができました。
nanoに対してきっかけを与えてくださった方はもうすでにこの世にはいませんが、
よりこのいただいたきっかけを紡ぐことを会社全体で決めています。
タイトルに戻りますが
「体現する気のない理念ほど無駄なものはない」です。
各企業、各個人が必ず自身の言葉に責任を持ち続けることを会社のルールとして決める。
理想の組織作りへの一歩は定義するところから始まるのかもしれません。