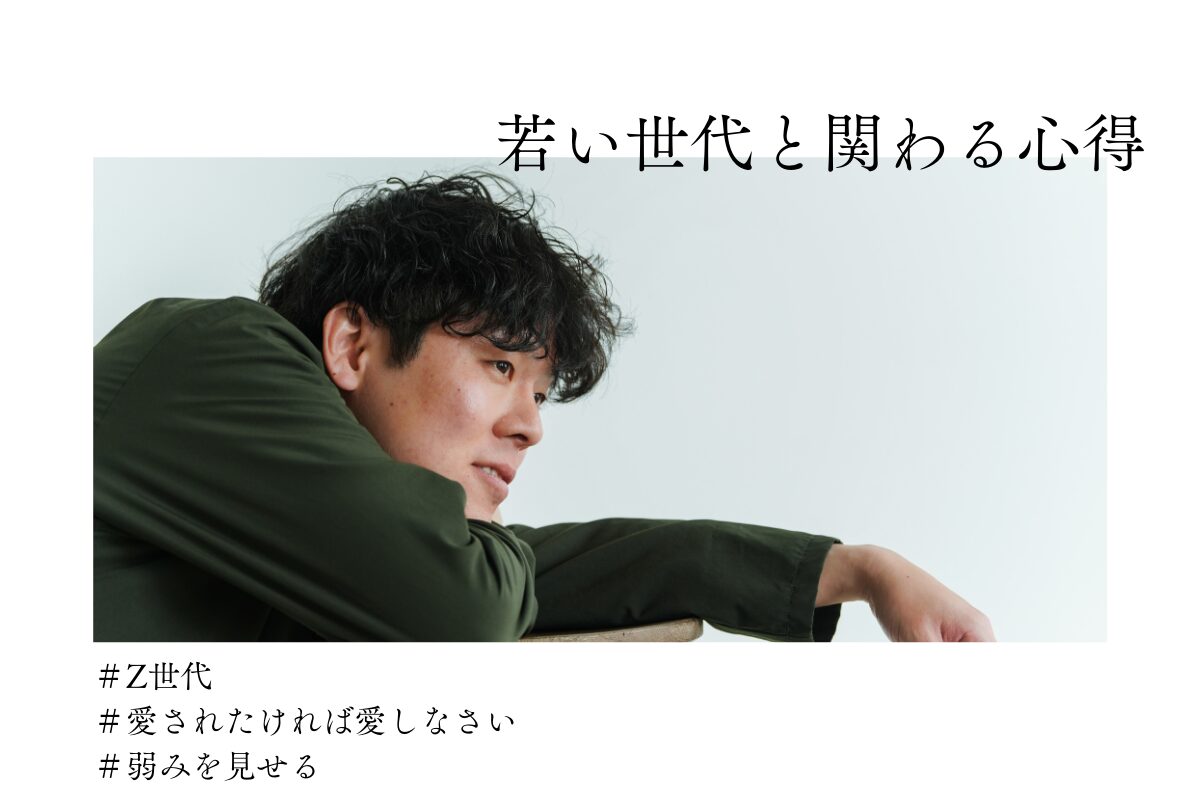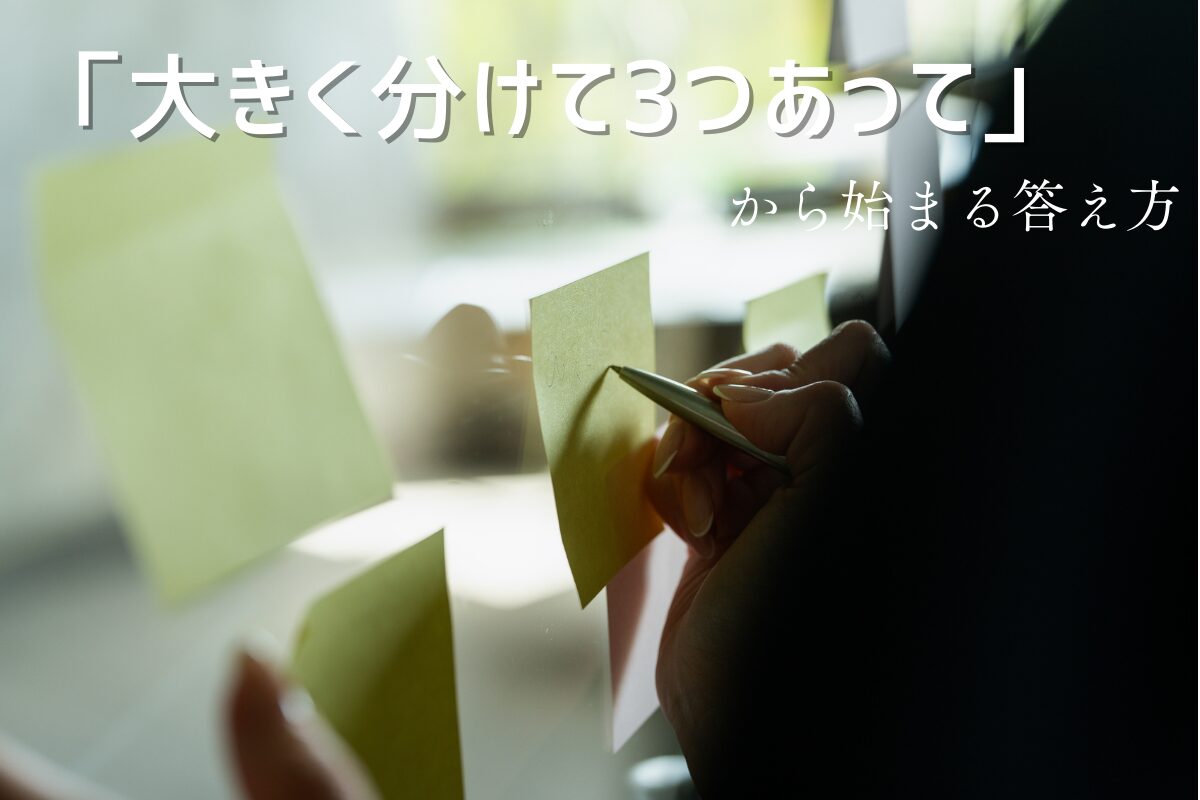ブログ
質問力の磨き方
パーソナルリブランディング
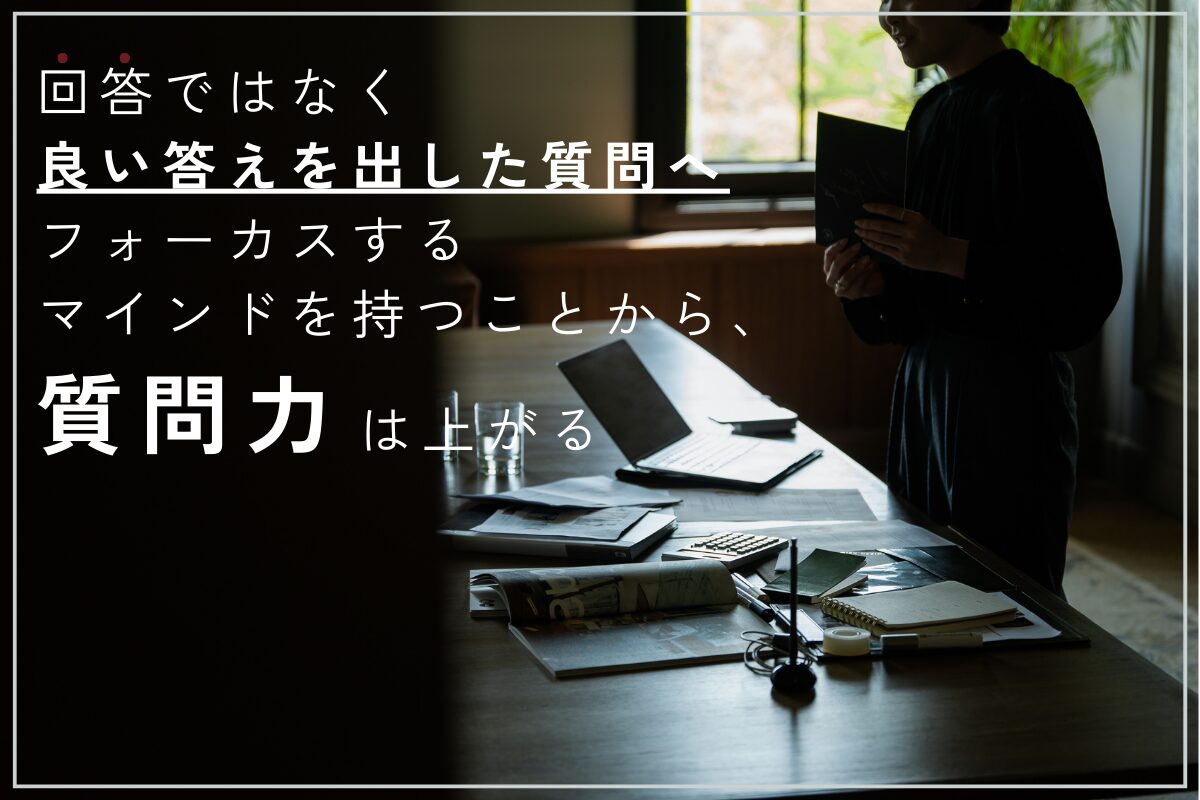
仕事に向き合う皆さまが、これまでのビジネス人生を通して必ず経験していると思われる質問での失敗。
目上の人と話す時や、ここぞという会議や対談の時、
「あー、なんでこんな質問しか出てこなかったのか、、、。」と
チャンスを無駄にしたことが何度もあるのではないでしょうか。
テレビで見かける記者会見でさえ、ただ人を怒らせるだけの無駄な質問をしている光景も度々目にします。
外から見たらすぐにわかるはずの「良くない質問」
いざ自分がするとなるとできないものですよね。
今日はこの「良くない質問」を磨き、「良い質問」に変える方法。
そんなブログをお届けできればと思っています。
答えより質問に注目してみる
まず前提として、質問力にはレベルがあります。
私も何度も経験している講演時の質問タイム。
会場が盛り上がる質問と明らかに空気の変わる悪い質問があります。
例えば悪い質問とはどのような質問か。
1つは〈抽象的すぎる質問〉です。
・「今日の講演会はどうでしたか?」
・「最近どう?」
あまりにも大きな範囲で問い、何から答えるべきか悩む問いには、回答者は気持ちよく答えることはできません。
もう1つは〈自分の意見を言いたいがための質問〉です。
問いを投げかけ、回答者が答えた後に、
そこに食いつき気味に反対の意見を投げつけたり、話を聞き終える前に次の質問に飛んでしまったり。
あまり気持ちの良い空気にならないことは想像できます。
では質問のレベルを上げるためにはどうすれば良いか。
それは「答えより質問に注目してみること」です。
会場が盛り上がる回答には当然、回答者の話術や伝える力が影響してきます。
ただその盛り上がるきっかけを与えた質問が必ずあります。そこに注目してみると、視点が変わります。
【 回答者ではなく、質問者へ 】
回答ではなく、良い答えを出した質問へフォーカスするマインドを持つことから、質問力は始まります。
ー なぜ今盛り上がったのか?
今の質問はレベル2の質問なのか?それともレベル10の質問なのか?
この判断ができるようになると、自分にもレベル10の盛り上がる質問ができる可能性が出てきます。
話し手は常に相手のレベルに合わせる
質問というものは、バリバリのビジネスマンやインタビュアーに必要なスキルで、私たちには必要ない、
そう感じる人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。
質問は絶対的に自身の成長に必要となります。
というのも、質問は必ずといっていいほど、「自分より優れている人」に対してすることが多くなります。
優れた人の信じられない感覚、想像もできない経験、思いつくはずのない発想。
優れた人から良い答えを引き出すには、「良い質問ができるかどうか」にかかっています。
・腕のいい料理人が家でも絶品料理を出してくれるか
・大成功している社長がなんの関係もない他人に素敵な話をしてくれるか
答えはNOです。
「話し手は常に相手のレベルに合わせる」これが現実です。
すごいスピードで投げられるピッチャーは、ゆっくりでも投げられるものですし、
受け取り手のキャッチャーを見て判断をし、投げるスピードを調整します。
「あなたには話すよ」
そう心を預けてもらえることが、良い答えを導く条件となります。
どれだけチャンスを掴み、憧れの人に会えたとしても、
良い答えをもらう準備ができていなければ、とんでもないミスを犯してしまうかもしれません。
質問力は磨けば伸びる
でも諦める必要はありません。質問力は磨けば伸びます。
質問力は、決して才能でもなければセンスでもありません。
質問力のメカニズムを理解することが大切です。
自分自身で良い質問なのか悪い質問なのかをチェックすることができ、判断できる、この能力を磨きます。
磨き方を2つお伝えしようと思いますが、
まずは私が経験した中で最も質問力の伸びを感じたゲームについて。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
⑴質問ゲーム
40人のクラスだったとして、5人×8チームをつくり、1チームごとに「好きな本」「好きな映画」など、
テーマにこだわらず自由なプレゼンを2〜3分で行います。
その後、残りの7チームの代表がそれぞれ質問をしていきます。
となると常に、プレゼンターへは7つのチームからの質問が集まることになります。
ここへの答え方は重要であり、重要ではありません。
7チームを終えた後、質問者たちではなく、プレゼンターへ
「どの質問が1番良い質問でしたか!」と聞き、これを繰り返していきます。
どのチームが質問賞を取れるかを競う、そんなゲームです。
良い質問をした人を評価する目的が1つと、
プレゼンをした本人が良いか悪いかを判断する目的が1つあります。
これを繰り返すと自然と、良い質問とはなんなのか、この感覚が段々と研ぎ澄まされていきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
⑵傍聴ディスカッション
10人のクラスだったとして、1対1のディスカッションを行い、残りの8人は回りで見学をします。
見学しながら、
・「あっ、こんなことで盛り上がってるな」
・「でもこの盛り上がりの起点をつくったのはあの人の質問だな」
という風に、俯瞰して見ます。
自分が話し手になると、もう話すことで手一杯になるのは当然です。
スポーツ観戦も同じくです。
明らかにレベルが違うにも関わらず、応援者たちが様々な意見が言えるのは、あくまで選手たちと同じ目線ではないからです。
素人がプロに文句を言える理由はここにあります。
人の質問を外から見る。
実はこの機会は日常にあまりありません。
飲食店でのカップルの喧嘩を楽しめてしまうのも、似た理由かもしれませんね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
もちろんまだまだ質問の磨き方には方法はあります。
今後のMad.ブログでもお伝えしていきますが、
まずは「良い質問をすることでの自己成長」を感じていただける方が、1人でも増えることを願っております。